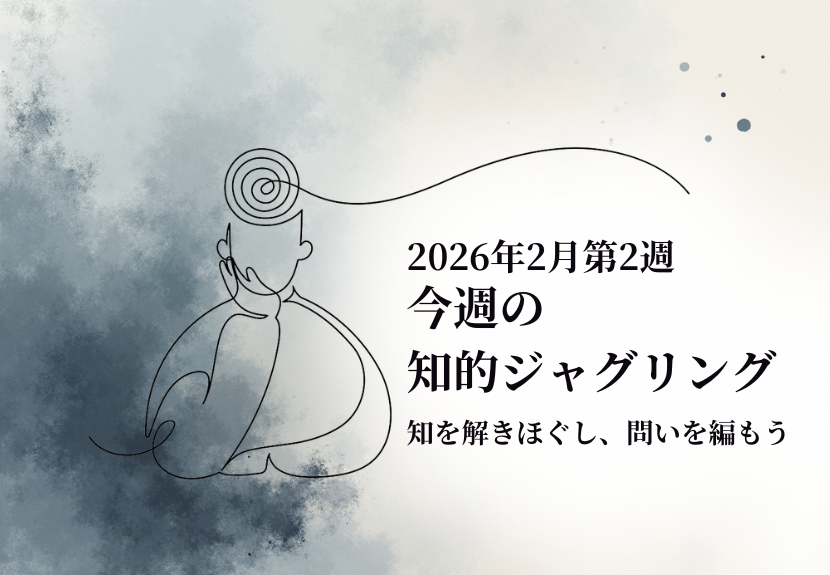
今週の知的ジャグリング|2026年2月第2週
今週は、電通グループの3100億円に及ぶ減損や日産の赤字予想といった「過去の拡大モデル(期待の資産)」の清算が相次ぐ一方で、輸送株への資金循環やアマゾンによるAI市場設計など、抽象的な物語から具体的な収益(実利)へと、資本の視線が激しく移動した一週間でした。 「仕組みが守ってくれる」という幻想が崩れ去る中で、私たちは組織として、あるいは個人として、いかにして「持続可能な主導権」を自らの手に引き戻すべきなのか
ブログ
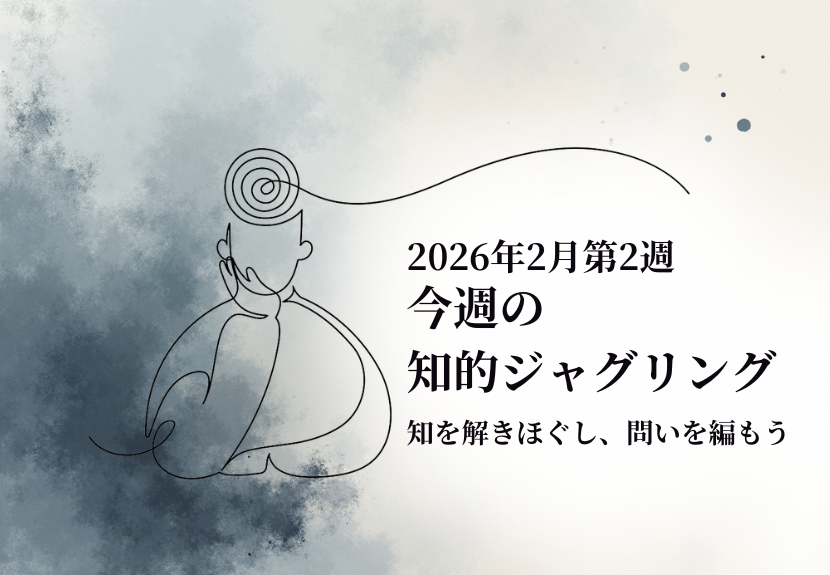
今週は、電通グループの3100億円に及ぶ減損や日産の赤字予想といった「過去の拡大モデル(期待の資産)」の清算が相次ぐ一方で、輸送株への資金循環やアマゾンによるAI市場設計など、抽象的な物語から具体的な収益(実利)へと、資本の視線が激しく移動した一週間でした。 「仕組みが守ってくれる」という幻想が崩れ去る中で、私たちは組織として、あるいは個人として、いかにして「持続可能な主導権」を自らの手に引き戻すべきなのか
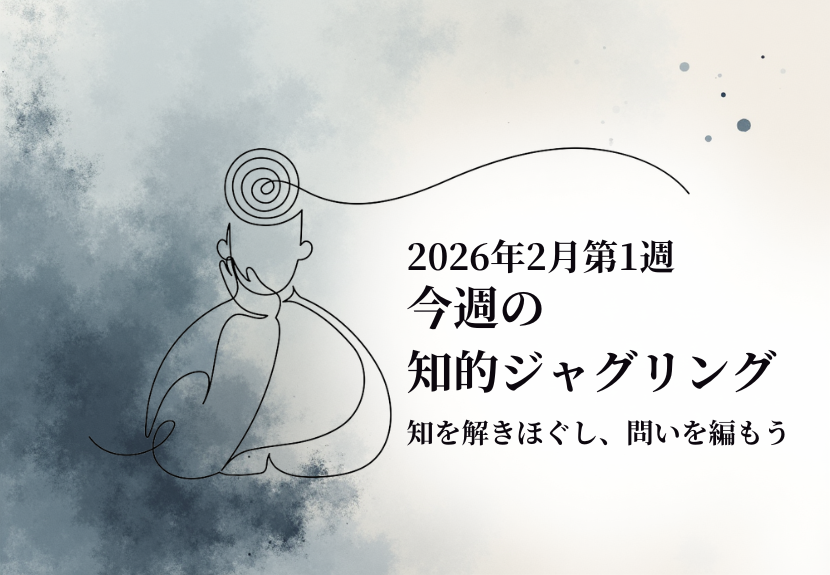
今週は、SUBARUの下方修正が突きつけた「特定市場への依存」のリスクや、トヨタの社長交代に見る「実行への重心移動」、そしてキリンのバーボン売却など、慣れ親しんだ「依存先」を問い直し、自らの足場を自律的に整え直そうとする動きが際立った一週間でした。 「外部のルールや過去の成功」に身を委ねる危うさが露わになる中で、私たちは組織として、あるいは個人として、いかにして変動に耐えうる「独自の構え」を構築すべきなのか。 今週のコメントから読み取れる4つの視点で、知をジャグリングしていきます。
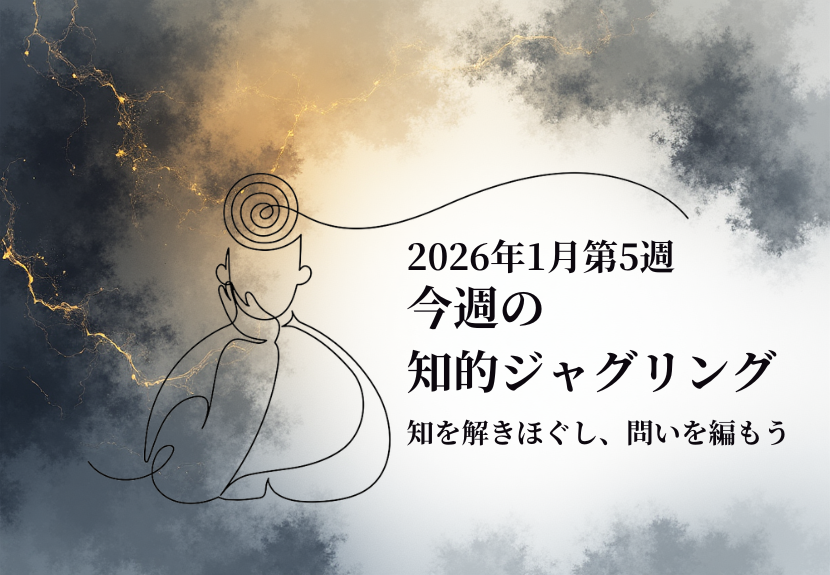
今週は、次期FRB議長人事を通じた「独立性」の政治的取り込みや、日立による長年の事業売却、そしてAIによる知的労働の前提崩壊など、長く信じられてきた「制度」や「枠組み」が音を立てて解体された一週間でした。 「仕組みが守ってくれる」時代が終わりを告げる中で、私たちは国として、企業として、あるいは個人として、自らの足場をどう「再設計」すべきなのか。 今週のコメントから読み取れる4つの視点で、知をジャグリングしていきます。
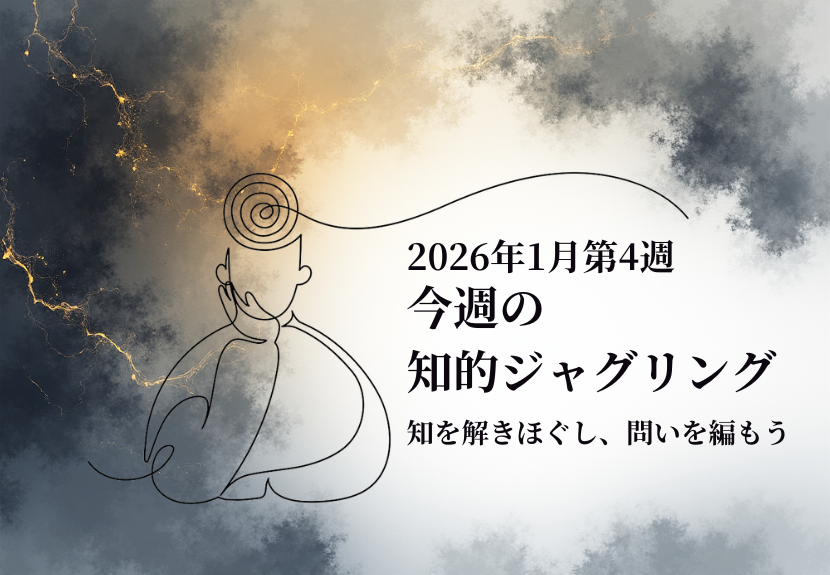
今週は、米国による「防衛費GDP比5%要求」や、資源を金融資産として管理しようとする「ドンロー主義」の台頭など、かつての「同盟」や「理想」の枠組みが、剥き出しの「取引」へと変質した一週間でした。 「同盟だから守られる」という幻想が崩れ去る中で、私たちは国として、企業として、あるいは個人として、いかにして実体のある「主導権」を取り戻すべきなのか。
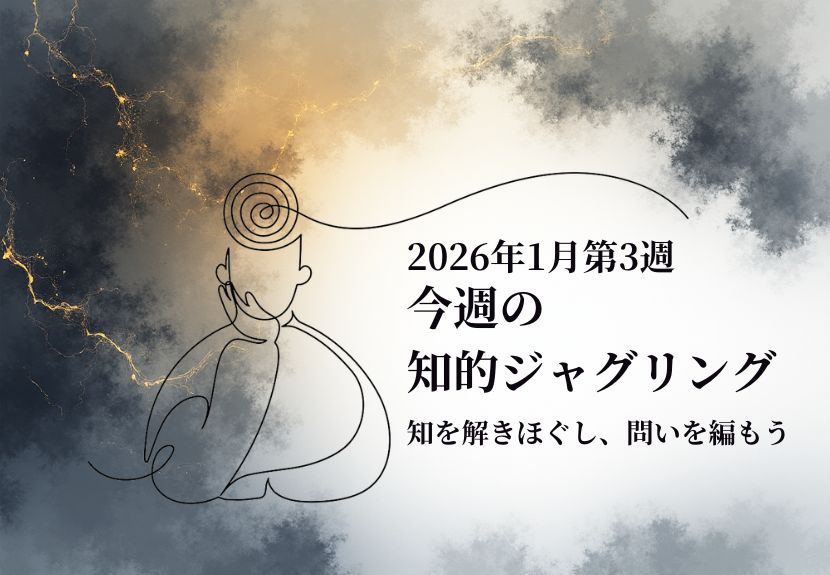
今週は、FRB議長への刑事捜査やメキシコへの軍事圧力など、既存の制度や国家主権という「防波堤」を、力によって塗り替えようとする強権的な動きが加速しました。 一方で、三菱電機の事業売却やAppleのAI戦略の転換など、自らの「立ち位置」を冷静に見極め、不透明な時代を生き抜くための「自律的な生存戦略」もまた鮮明になった一週間でした。 外側から押し付けられる「力の論理」に思考を委ねるのではなく、自らの「専門的な良心」をアンカー(錨)として、不当な介入を撥ね退ける「個の強さ」をどう構築していくのか。
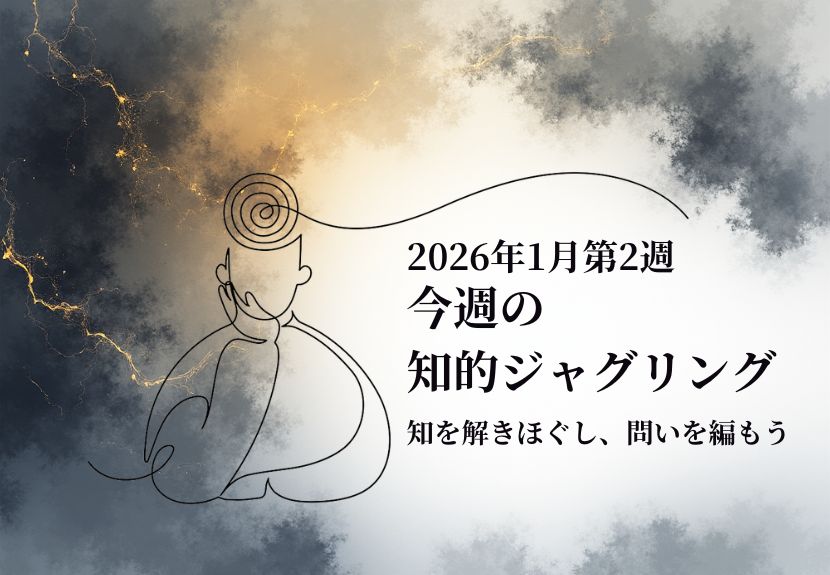
今週は、ベネズエラへの電撃的な介入の「その後」が語られ始め、国際社会が「力の論理」の代償に直面した一週間でした。また、米国の労働生産性急上昇やエヌビディア対抗馬の出現など、AIが経済のOSを書き換えるスピードがさらに加速しています。 巨大な力学が「安定」や「効率」の名のもとに現状を塗り替えていく中で、私たちはどこまで「責任の解像度」を保ち、自らの「思考の筋力」で違和感を言語化し続けられるのか。
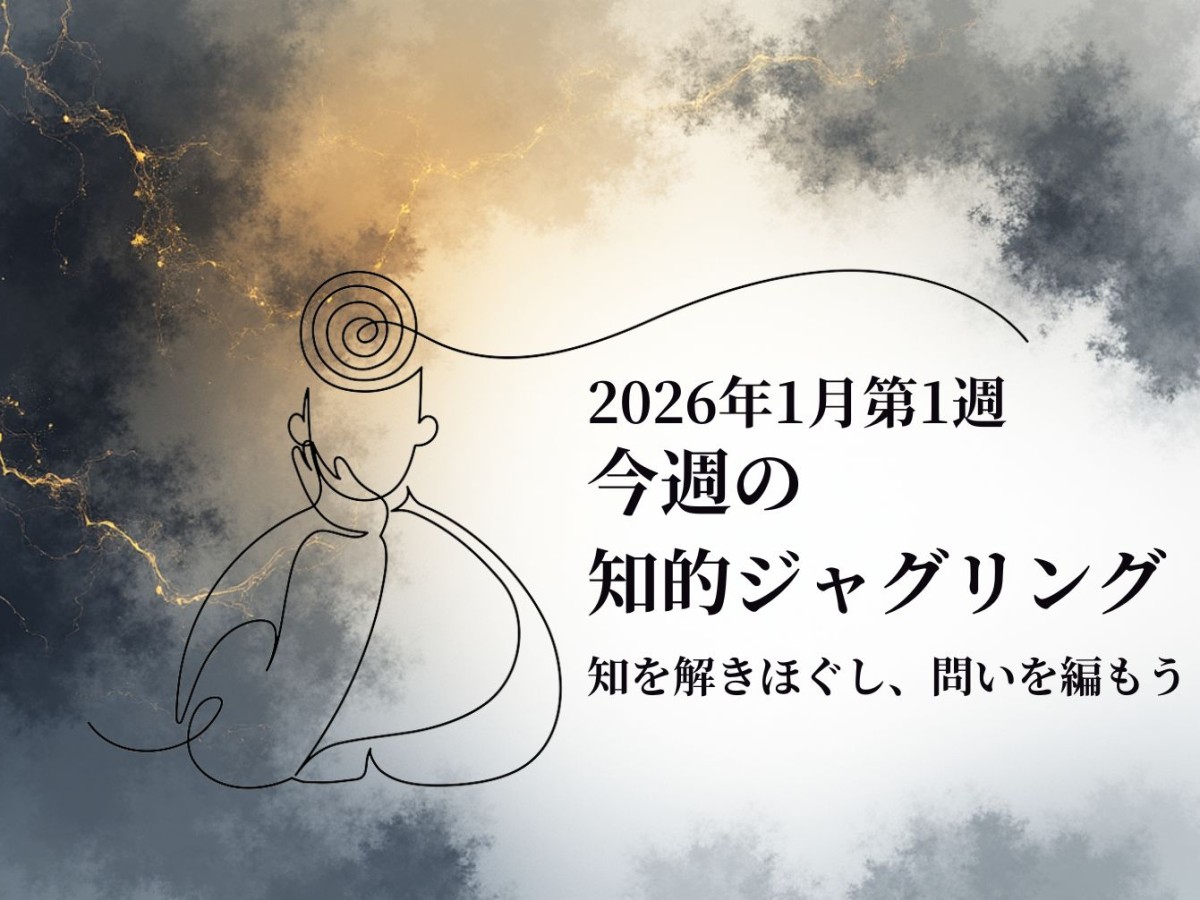
2026年の幕開けは、ベネズエラへの電撃的な軍事介入や中国資本への排除命令など、国際秩序のOSが「法の支配」から「力の論理」へと激変する衝撃的なニュースで始まりました。 一方で、個人の生活に目を向けると、単身高齢者のリスクやセルフメディケーションの課題など、制度の谷間で「どう生き残るか」という切実な問いが突きつけられています。 マクロな力学が個人の暮らしを呑み込もうとする今、私たちはどこまで「責任の解像度」を保ち、「複線的なリアリズム」で未来を設計できるのか。
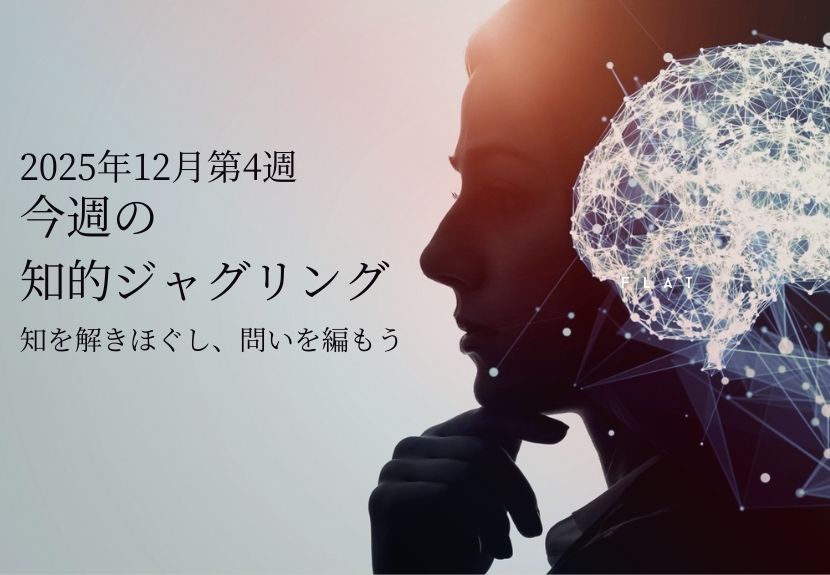
週は、日本製鉄による歴史的な買収交渉の舞台裏や、エヌビディアの防衛的なオープン戦略など、強者たちが自らの生き残りをかけて「ゲームのルールそのもの」を設計し直す局面が鮮明になりました。 同時に、DEIの形骸化への指摘や「睡眠」への投資といった視点からは、巨大なシステムに呑み込まれないための「個としての誠実さ」と「自己管理」の重要性が浮き彫りになりました。 外側から与えられた正解を追うのではなく、自ら「責任の解像度」を持って土俵を作り、自らの「思考の筋力」で納得のいく選択を積み重ねる。 そんな、真に主体的な戦略が問われた一週間を、4つの視点から読み解きます。
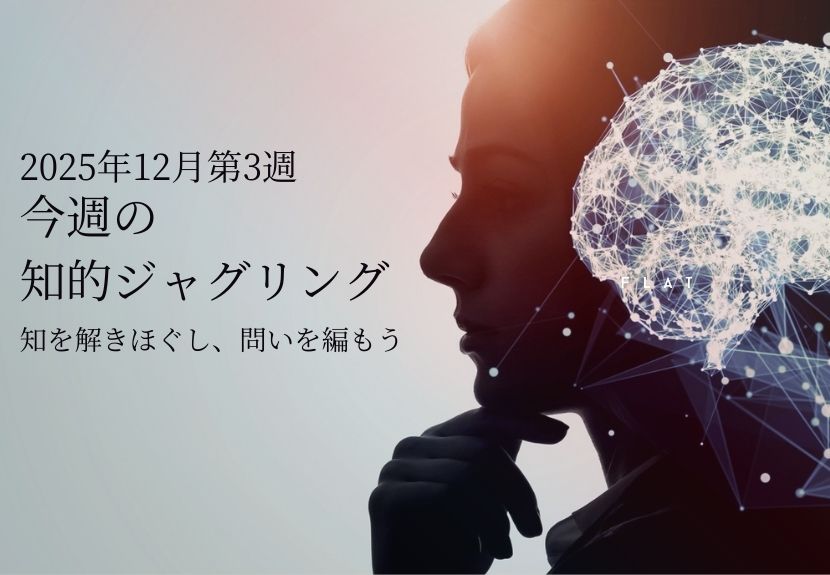
今週は、これまで「正解」として語られてきたDEIやEVシフトといった単線的な物語が、現場の歪みや市場の論理によって、より泥臭く複雑な「現実」へと回帰する動きが目立ちました。 便利な代行サービスや効率的なAI、そして形式的な肩書き。 あらゆるものが「プロセスの手触り」を奪い、責任を曖昧にしようとする中で、私たちはどこまで「思考の筋力」を保ち、「責任の解像度」を高めていけるのか。 今週のニュースを「複線的なリアリズム」で読み解く、4つの視点をお届けします。
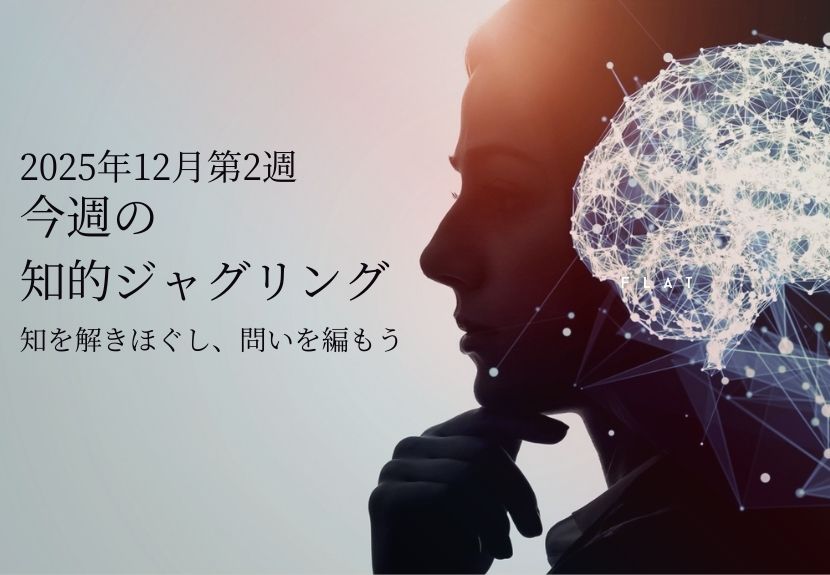
今週は、AIインフラへの巨額投資やIPの開放といったダイナミックな動きがある一方で、投資過熱への警鐘や個人の思考力の低下といった「副作用」にも焦点が当たりました。 正直に言うと、今週のニュースを追いながら私は、「このスピードに、人間の判断力は本当に追いついているのだろうか」という小さな不安を覚えました。 膨張するシステムと、有限な資本・人間の知性。このバランスをどう保ち、どこに勝機を見出すのか。4つの視点から、今週の知的ジャグリングをお届けします。