今週の知的ジャグリング|2025年6月第2週
今週のテーマは「構造を変える眼差し」
日本製鉄によるUSスチール買収の成功、MetaによるAIスタートアップの買収攻勢、セクハラ問題の構造的再定義、そして「問いを立てる力」への回帰。共通するのは、単なる出来事の表層ではなく、その背後にある構造を見つめ、変えるための行動を起こす眼差しです。未来を動かすのは、いつだって「仕組み」を見極める人の問いと意志です。 今週も、4つのPickをもとに知的ジャグリングをお届けします。
▶ 1. 日本製鉄、USスチールを手中に
「日鉄、米政府と国家安全保障協定-USスチール買収成立予定と声明」(Bloomberg・2025/06/14)
「米政府がUSスチール黄金株保持へ、トランプ氏言明-日鉄の取引」(Bloomberg・2025/06/13)
米国の政治的逆風を超えて、USスチールの買収を成し遂げた日本製鉄。
この交渉の背景にあるのは、資源確保と経済安全保障の文脈。
そして何より、「日本企業も意志と戦略があれば世界で道を切り拓ける」という希望の事例です。
🧠 ジャグリングポイント:製造業×交渉戦略×国家関係
→戦略と意志が、世界を動かす。
▶ 2. セクハラは「倫理」ではなく「経済」の問題
「セクハラは『独禁法違反』 起業家団体、公取委に申告へ」(共同通信・2025/06/10)
セクハラを“モラルの問題”ではなく、“取引の公正性を損なう経済問題”として捉えた点に、私は新しさを感じています。この視点の転換が、ようやく本質的な議論の出発点になるのではないでしょうか。
さらに、「セクハラはブランド毀損や採用難、人材流出を引き起こす“構造リスク”であり、企業価値の根幹を揺るがす問題だ」として、企業がハラスメント対策に構造的なアプローチを取る必要性を訴えています。
🧠 ジャグリングポイント:ハラスメント×経済構造×信頼資本
→倫理だけではなく、取引の公正性を損なう経済問題。
▶ 3. 今週の“本屋さん”:問いが文化をつくる
「【ブックリスト】問いで組織を変える——マネジメントの原点3冊」(今日の本屋さん・2025/06/12)
今週、私は「今日の本屋さん」として、このブックリストを紹介しました。「問い」は、未来を開く鍵だと私は思っています。 アート思考の研究を続けてきた一人として、そして経営の意思決定の現場にいる立場として、どんな場面においても「問い」が創造性と変革の出発点になることを実感しています。
経営の現場でも、家庭の中でも、そして一人の人間として生きていく上でも──「答えを出すこと」よりも、「問いを立てること」のほうが、はるかにエネルギーが要ります。そして、はるかに可能性を持っています。
問いは、関係性の質を変え、行動の方向性を変え、「どんな未来を生きたいのか」を静かに教えてくれます。 今回紹介した3冊は、問いを通じて組織や自分自身のあり方を見つめ直すヒントになる一冊ばかり。「問いを立てる力」が信頼や組織文化の基盤になることを改めて確認する機会となりました。
🧠 ジャグリングポイント:問いの力×組織文化×関係
→ 問いが、未来をひらく。
▶ 4. Meta、“構想する力”への投資
「米メタが2兆円出資でAI新興のCEO獲得、業界の注目は『超知性ラボ』以外の波紋」(Forbes JAPAN・2025/06/14)
「メタ、スケールAIに143億ドル出資 CEO迎え入れ=関係筋」(Reuters・2025/06/13)
「メタ、AI開発の遅れ挽回に本腰-スケールAIへの2兆円投資を決定」(Bloomberg・2025/06/13)
私はこのニュースに複数回コメントしましたが、注目したのは「構想する力を持った人材」への投資姿勢です。 生成AIがコモディティ化し、モデルの差異だけでは優位性を保てなくなっている今、競争軸は「誰と、何を創るか」に移っています。Metaが獲得したのは技術だけでなく、ビジョンを描ける人材であり、そのリーダーが率いるチームの創造力です。
この動きは、「資本が構想を買う」構図として象徴的だと感じました。AI時代において、“構想する力”こそが競争力の本丸になっていることを強く印象づける出来事でした。
🧠 ジャグリングポイント:AI覇権×人材戦略×スピード競争
→構想力が、競争力になる。
✍ 今週の総まとめ:構造を変える眼差し
日本製鉄、セクハラ問題、MetaのAI人材獲得、そして「問いを立てる力」── 一見異なるようで、すべてに共通していたのは、「構造をどう見つめ直すか」「変化をどう設計するか」という視点でした。
未来を動かすのは、出来事ではなく、それを支える“仕組み”と“構想力”。 いま必要なのは、目に見えない構造の変化を見抜く問いの力です。
来週もまた、社会を知的に読み解くヒントをお届けしていきます。
知を解きほぐし、問いを編もう。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
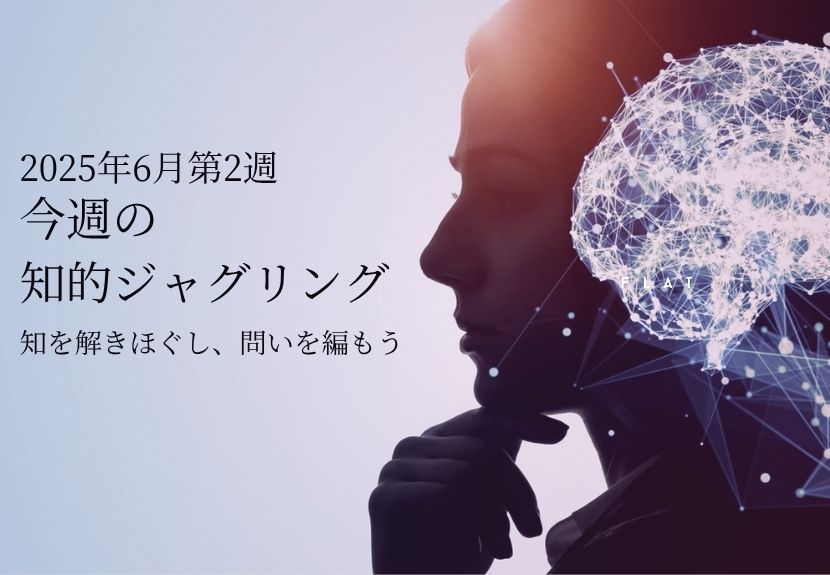

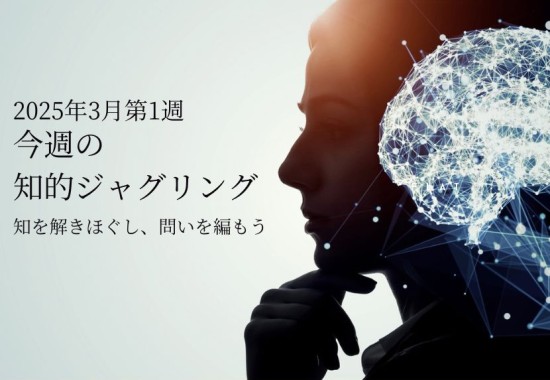
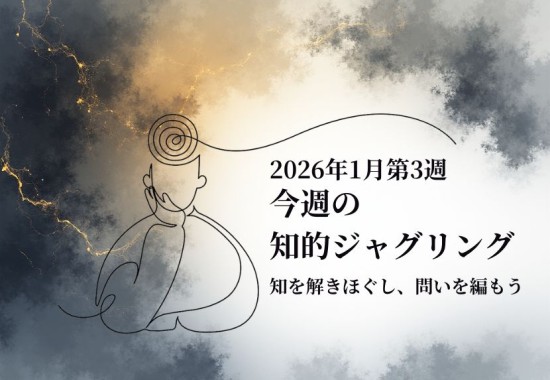
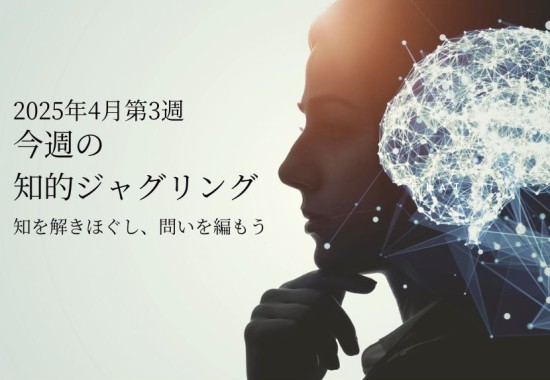
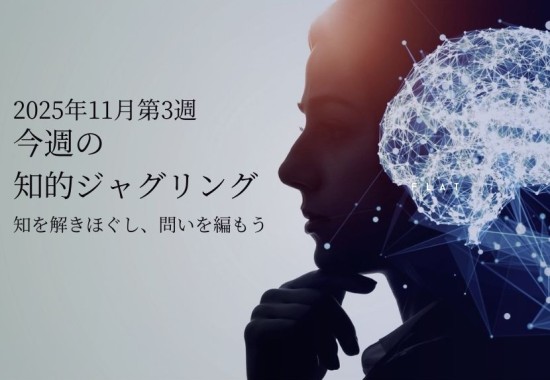

この記事へのコメントはありません。