ジョルジュ・サンド
 とても先進的なセンスを持った友人が先週他界しました。あまりに早すぎるその死をなかなか消化できず、彼女がとても好きだった作家、ジョルジュ・サンドを読み返したり、映画を見たりしています。ここ数年、自分と同年代の近しい友人たちが次々と他界する中、自分らしい生き方は何かを問わずにはいられません。そして、皆、同様に、「自分のためだけに生きず、誰かのためにも生きてほしい」と言い残して行くところに、胸が詰まります。
とても先進的なセンスを持った友人が先週他界しました。あまりに早すぎるその死をなかなか消化できず、彼女がとても好きだった作家、ジョルジュ・サンドを読み返したり、映画を見たりしています。ここ数年、自分と同年代の近しい友人たちが次々と他界する中、自分らしい生き方は何かを問わずにはいられません。そして、皆、同様に、「自分のためだけに生きず、誰かのためにも生きてほしい」と言い残して行くところに、胸が詰まります。
ジョルジュ・サンドの29歳からの数年間にスポットをあて、サンドとミュッセの恋愛を描くことで、サンドの一面を表した映画「年下のひと(Les Enfants Du Siecle)」を見ました。
内容(goo映画より)
1832年。29歳の女流作家ジョルジュ・サンド(ジュリエット・ビノシュ)は、夫と別居し、ふたりの子供を連れてパリへやってきた。そんな矢先、彼女はある朗読会で6歳年下の美貌の若き詩人ミュッセ(ブノワ・マジメル)と出会い、恋におちる。彼らの関係は文壇でスキャンダルとなり、ふたりは渦中を逃れてヴェネチアへ旅に出る。そこでふたりの前に現れたのが、病に倒れたサンドを診察した医師パジェッロ(ステファノ・ディオニジ)。病床でも生活のため執筆活動を続けるサンドを放って、ミュッセは夜遊びに出歩き、酒とアヘンに溺れたあげく倒れた。サンドは献身的に彼を看病しながらも、一方で優しいパジェッロと関係を深めていく。嫉妬に狂ったミュッセは単身パリへ戻るが、あきらめきれない彼は、パリへ戻ってきたサンドに情熱をぶつける。サンドも彼への愛を抱えながらも、ついにふたりは破局した。かくして、この恋はふたりの半生に良くも悪くも影響を及ぼしたのだった。
高校生の頃に愛読したジョルジュ・サンドですが、その頃は彼女の多面性があまり理解できず、どうしてそういう人生を送るのだろうと考え込んでしまったこともあります。大人になり、自分自身がいろいろな経験をしたことで、サンドの多面性が理解できるようになったこと、そして、サンドを演じたジュリエット・ビノシュがインタビューでも言っていたように、自分も彼女に近い性質を持っているのだと思うところも多数あるからか(若い頃には気づきませんでした)、若い頃よりももっと共感を持ってサンドの生き方を理解できる。そして、その気持ちを持って、サンドの作品を読むと、若い頃には見えていなかったものが見えてきて、深みを感じます。
ミュッセの苦しみがもっと細かく描かれていると良かったのですが、サンドの視点が重視されていたのかもしれません。
 サンドの代表作「愛の妖精」。
サンドの代表作「愛の妖精」。
内容(「BOOK」データベースより)
フランス中部の農村地帯ベリー州を背景に、野性の少女ファデットが恋にみちびかれて真の女へと変貌をとげてゆく。ふたごの兄弟との愛の葛藤を配した心憎いばかりにこまやかな恋愛描写は、清新な自然描写とあいまって、これをサンド(1804‐1876)の田園小説のうちで屈指の秀作としている。
サンドの繊細な面が非常によく表現されている小説。フランスの地方出身だった彼女だからこそ描けた小説ではないかと思います。
暖かい優しさとは何か?を問いかけてくるような作品だと思います。
フェミニストで男装の麗人として知られるようになったサンドですが、そして、ミュッセだけでなく、リストやショパンなどとも恋愛関係を持ち、その奔放な人生がピックアップされることの多い彼女ですが、繊細な心と女性らしさを誰よりも知っていた人なのではないかと思います。そして、そこに友がなによりも惹かれていたことは、彼女がいなくなった今だから分かることかと思うと、寂しさと悲しさに胸が締め付けられます。
女性としてどうしたら幸せに生きられるのか?
年代を超えた大きな疑問に対し、私は死を前にしたときにどう答えられるのか、これから答えを出して行くべきことなのではないかと思いました。
友の冥福を祈ります(合掌)。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
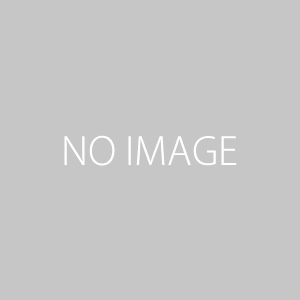
この記事へのコメントはありません。