吉田松陰・留魂録
 昨夜、友人が夕食を食べに来た際、いろいろな話から自分の葬儀をどうしたいか?という話になりました。
昨夜、友人が夕食を食べに来た際、いろいろな話から自分の葬儀をどうしたいか?という話になりました。
友人が帰った後、自分の死生観についてあれこれと考えてしまい、遺書文学の最高峰と言われている「吉田松陰・留魂録」を読み直す。
解題、本文と現代語訳、松蔭の史伝、という3部構成で書かれている本書は、吉田松陰が安政の大獄に連座し、牢獄で執筆した「留魂録」を学ぶことのできる書。
処刑前日の極限状態の中で書かれたものという特殊事情があったにせよ、わずか29歳でこれを書き上げてしまうとは、すごいと思うと同時に、私はいったい何をやってるんだ!?と自分に喝を入れたくなります。私とそう年の変わらない世代の人が、特殊な事情があったにせよ、これだけのモノを残せているのだから...
全く同じことを、橋本左内の「啓発録」を読んだときにも思ったのですが...
「留魂録」はわずか5千字。さくっと読める長さだけれども、その重みたるや、計り知れない。
個人的には、「今日死を決するの安心は四時の循環に於いて得る所あり。蓋し彼の禾稼(かか)を見るに、春種し、夏苗し、秋苅り、冬蔵す。」ではじまる第8章は彼の死生観を穀物の収穫に例えて語ったもので、心に深く突き刺さりました。
#現代語訳:「今日、私が死を目前にして、平安な気持ちでいるのは、春夏秋冬の四季の循環ということを考えたからである。つまり農事を見ると、春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。」
「私は三十歳、四季はすでに備わっており、花を咲かせ、実をつけているはずである。それが単なるモミガラなのか、成熟した粟の実であるのかは私の知るところではない。もし同志の諸君の中に、私のささやかな真心を憐み、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種子が絶えずに、穀物が年々実っていくのと同じで、収穫のあった年に恥じないことになろう。同志よ、このことをよく考えてほしい。」
「死して不朽の見込みあらば、いつ死んでもよし」という死生観を持っていた吉田松陰は、処刑という形で死を迎えることで、先駆者としての本当の役割を果たしたのではないか。キリストと同じに語るとクリスチャンからおこられるかもしれないが、受難者像を確立することで、この遺書に説得性を持たせたのではないかと思う。
こういう生き方もありだとは思うのだけれど、生きて、生き延びてなんぼではないかとも思ったりするのでした。
ただ、どんな人にでも平等に訪れる死とどう対決するのかについては、吉田松陰の思想も生き方もいいなぁと思います。
...なぞととりとめなく、いろいろと考えていたら、珍しく寝不足になってしまいました。今日は早くベッドに入ろう。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
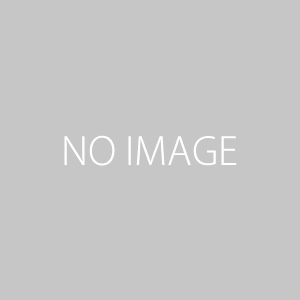
この記事へのコメントはありません。