マドンナ・ヴェルデ
 先日読んだ海堂尊さんの「ジーン・ワルツ」の裏ストーリー「マドンナ・ヴェルデ 」を読みました。
先日読んだ海堂尊さんの「ジーン・ワルツ」の裏ストーリー「マドンナ・ヴェルデ 」を読みました。
内容(「BOOK」データベースより)
「ママは余計なこと考えないで、無事に赤ちゃんを産んでくれればいいの」平凡な主婦みどりは、一人娘で産科医の曾根崎理恵から驚くべき話を告げられる。子宮を失う理恵のため、代理母として子どもを宿してほしいというのだ。五十歳代後半、三十三年ぶりの妊娠。お腹にいるのは、実の孫。奇妙な状況を受け入れたみどりの胸に、やがて疑念が芽生えはじめる。「今の社会のルールでは代理母が本当の母親で、それはこのあたし」。
「ジーン・ワルツ」を理恵の母親のみどりの視点で書いた作品です。前作は不妊治療を描いたけれど、今回は「代理母」を扱った作品で、前作よりも、重苦しい空気の流れる作品です。理由は、本作品では、産婦人科医である曽根崎理恵が行った代理出産は、認められていないことを次々と行ったことで、倫理問題を多く抱える作品になっているからだと思います。例えば、夫(後に離婚、たぶん離婚が前提だったのだろう)と不倫相手から、同意を得ずに精子を採取したり、不妊治療患者に対して、本人の同意を得ずに自分の受精卵を混ぜて体内へ戻し、結果、その患者が妊娠したことなど。代理母はまだ日本では認められていませんが、特殊なケースであればやっている施設もあるわけなので、それだけであれば倫理すれすれだとは思うのですが、それ以上、踏み越えてはいけないエリアまで踏み込んだのに、それに対する結末(特に他人に自分の受精卵を入れたこと)は放置されている点が、この重苦しい空気を作っているのだと思います。
生殖医療への賛否両論はあると思いますが、産む選択肢の1つであることは間違いなく、どうしても子供が欲しいけれども恵まれない人たちの最後の望みの綱になっており、この技術によって救われている人は数多くいます。それをこのような作品を書くことで、世に知らしめてくれるのはいいのですが、このような書かれ方をすると、生殖医療の闇だけが取りざたされるのではないかと、すごく不安に思いました。
この秋に「ジーン・ワルツ」が菅野美穂さん主演で映画公開されるそうですが、正しいメッセージが世の中に伝わることを願ってやみません。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
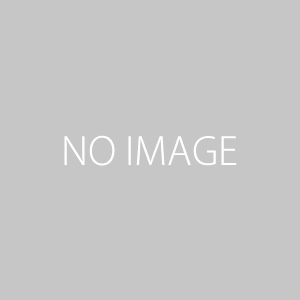
この記事へのコメントはありません。